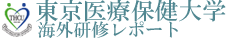

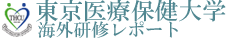

| 1893 | アメリカの在宅介護の始まり。 自己管理の仕方を指導していた。 リリアントモードが始めたと言われている。 |
| 1929 | コミュニティナースオブシアトルが設立。 ここはシアトルで1番創めの在宅ケア会社である。 営利目的ではなく非営利組織であった。 1年間の訪問 21740件 訪問はじめに掛かる費用 1.25$ 2時間目 +0.75$ 夜・休日 1.50$ Visting Nurse Services of the northwest この会社は女性3人が立ち上げたものである。 |
理学療法士・作業療法士・言語療法士・ソーシャルワーカー・ 看護士・準看護士・ヘルパーが働いている。
| 現在の雇用 | 223名 | ||
| 看護師 | 80名 | ソーシャルワーカー | 3,4名 |
| 理学療法士 | 40名 | 準看護師 | 5名 |
| 作業療法士 | 5名 | ヘルパー | 6名 |
| 言語療法士 | 3,4名 | ||
| 訪問 | 98423件 |
| 患者 | 6684名 |
| インフルエンザ患者 | 45560名 |
| チャリティケア | 1658639$ |
チャリティケア:コミュニティに入っていない人。お金が無く、条件を満たしている人には無料
病院より家出のケアを望む人が多いと考えている。また、病院ケアよりも在宅ケアより負担費用が少ない。 そのためこれからは在宅ケアに向かうと見られている。 ITヘルスケアが発達し、手書きの記録を基に請求をしていたものが電子化される。 実際に訪問する人がオフィスに行かず訪問先に直接行けるようになった。 しかし在宅ケアが増えるにつれ問題もでてくる。
団塊世代がケアを必要とし、需要が増えるとともに看護士、理学療法士が不足。 専門家雇用は医療に対する知識を要し、ソフト・ハードとも知識を持つ人材が必要になる。 コンピューターのシステムダウンにも対応できるよう考えなければならない。
新人ではPCが使えない者もいる。また普段使うPCとは異なる点がある。
そのため4日間集中トレーニングを行う。
PC記録は直接フォームには入らない。コピーして1日2回アップロードする。
利用者(サブスクライバー)はボタンを首からかける。 緊急時等このボタンを押すと自動的にセンターに連絡され30秒以内に話ができるようになっている。 モニターしている人と話ができる機器も同時に設置される。


利用者の95%が救急でない。誰かと話がしたい等可能なものであれば24時間、1日の回数制限が無く使うことができる。 ちょっとしたケアが欲しいのであればどこに連絡したらいいかを指導。
5%は救急で、救急にいくかどうかのプロトコルがあり救急救命士が病院に行くかを決める。 モニターしている人が利用者の地元の消防署に連絡し状態を伝える。
話せない人、ボタンを押してから反応が無い人に対し,
7回電話
→反応がない
→リスポンダーに連絡
→いない
→消防署に連絡
病院にいった際、24時間以内にFAXで連絡される。この利用者が帰ってこられる状態であればまたライフラインを利用する。
利用者は基本的に在宅ケアを受けている人だけでない。ライフラインの使用のみもできる。石の処方契約もなくてよい。
若い障害もちの利用者もいる。
病院は医師から情報がFAXで送られてくる。→内容をデータベースに入れる(一般情報・保険に加入しているか・体の状態・知っておくべき自宅情報)
これらをアドミッション部が記録し、実際に在宅ケアに向かう人にハードコピーが渡される。支払いは事前に許可を要するものか?
またその支払いに上限はあるか?何回の訪問で終わるか?等も記載されている。
ここでは1日2回アップロードされる情報と時間のギャップがあること。リアルタイムではない。
医師が在宅情報を変更すれば記録してある情報とは異なってしまう。→電話やFAXで連絡し、連絡事項をまたデータベースに記録。
ドクターのオーダーもつくる。
医師にチェックしてもらう。(同じフォームで作成するからデータベース化は容易)
ポータルはあるにはあるがまだ使われていない。
家から出られない人に限り受けられる。
Care conditionをみる(入院⇔在宅ケアを無駄に重複してないか?)
どういった診療科の人が必要か?→ケア計画、これからの方向、能力
国の標準←採点される
何回患者が病院に運ばれたか?
1,2年後パフォーマンスに対しての支払い。いいケアに対してはいい支払いがなされる。
患者のアウトカムで支払いが80%が平均的。
10%がよいケアでボーナスが出る。残りの10%はよくないケア。
日本ではいいケアをすると料金は加算される。
医療ITが進む→記録に一貫性を持たせることができる。
保険と病院が一体(こういったシステムの走りでもある)となり会員制。
45年前からトリアージの概念はあり、当時から救急の過剰使用が目立ったために始まったシステム。
日本では医師会が強いためこういった決定権が看護師たちに与えられていない。
アメリカでは余計な医療に掛からなくてもいいよう医師が看護士をサポートした。

24時間365日年中無休
医療に関する事ならいつでもOK。
看護士は遠隔で7−8名
遠隔利点
患者の状態でどのくらい緊急か仕分けすること。
どこに連絡したらよいかをトリアージしてあげる。
診療所から他の医師の紹介や、時間外診察したい場合、重症ではないが不安な点がある時。
→これにより救急費用削減
目的は正しい認識の教育、医療の無駄使いを防ぐ。
患者が救急に電話した際、実際には救急につながらずコールセンターにつながる。
標準化されたものでトリアージするため受け答えする看護士が違っていても同じ答えを返し一貫性がある。
電話がきたら、住所、一番重症だと思う症状を聞く。→これが一番大事。これを基にガイドラインの選択をする。
一回の電話で8,10分ほど時間を使う。
保険の状態はトリアージする人にはわからないからここではかけることが出来ない。
救急車も無料ではないため使用できない人もいる。
医師紹介は医師と契約しているので断る権利はない。
トリアージ情報は人間が持っていて、他はインターネット上にある。ドクターが患者に説明するための情報もある。
トリアージにはお年よりなどバラエティがあり、レポートも様々なタイプのものが出せる。
トリアージする人は患者フォローのためにいる。
わからないことはわかるまで質問、迷うことは無い。(←これは新人が判断つかない時にとる行動とは矛盾?)
ランゲージバンク(この地域で共有している)と契約している。
病院の中で多くの人が話すような言語であればその人を介し会話もするが、使う人が少ない言語であればランゲージバンクを通す。
シアトルの保健所、診療所などは37ヶ国語話せるようになっているところがあるのでこちらにお願いすることもある。
東アジアの言語は政府が通訳をやっているのでなかなか使えない。東部のヘルスケアでは様々な言語が多い。
ソフトの使い方、臨床症状の教育。
新人で判断が付かない場合は2を選択するよう教育される。
ここで働けばナースの答えを聞いて数年で判断が付くようになる。
ITが医療に入る→プライバシーの問題
アメリカ:記録の法律
テレホントリアージの法律があり、電話で話すことはお互いに記録できる。(23州)
トリアージで会話を聞かれることがあるがその内容を保護しなければならない。
英語以外の人に言語が通じるようサービスすることも法律で規定されている(6ヶ国語)
翻訳を機械で行う→エラー発生→この際責任はどこにあるか?
医療の国際法
Webで患者ケア→オーストラリアの法律に関わってくる
eHealthを使う
一般情報が欲しいのか、医療に関わっているのか
患者が医療サイトを閲覧
このサイト作成者は医療の情報提供とアドバイスは別と考えなければならない。
オンラインで薬の処理→法律の問題
これは以前よりインターネットの法律が増えたため問題は少なくなった。
アメリカでは医師がEメールを使い患者から予約・処方箋・検査結果・保険に関する質問を受ける。
安全性がしっかりしていればなおよい。
→安全性はどこまで確保できるか?メールを返信するまでの時間差が問題でないか?
医療情報技術認定委員会(CCHIT)
医療情報に関するソフトウェアは全て互換性がなくてはならないという考え。
新しい電子カルテはここの委員会の認定を受けなければならない。
医療崩壊の危機である原状を放置するとさらに今後の対策が大変になる。
クラブラントクリニックとグーグルが契約し世界中どこにいても情報を取り出せるようになった。
データをコンピューターに入れ医師のトリアージができる。
長期療養施設などでいつでも医師と連絡が取れるので安心してもらえる。
この研修でテレホントリアージの存在やトリアージする目的を知った。日本には無いシステムで、 まったく思いつかなかった概念であった。現在の日本でも医療費の無駄遣いが目立っている。 また日本人に多い感覚では、少しの不安があっても救急車を呼ぶほどではないと自己解決してしまい 大きな病気が潜んでいるかもしれない最初の小さなサインを見逃しがちである。このシステムはこういった日本人特有の不安を取り除き、 病気であれば早期発見を促し日本でも医療費の大きな削減につながる。
在宅ケアでは日本には介護はあるが医療にまで手を出せていない。遠隔治療が可能ならばこちらも大きな医療費の削減、 地域での医療格差をなくすことにつながるが現在のアメリカと同じように専門家の人手不足に悩みそうだ。 また電子カルテもまだまだ普及途中でありカルテの互換性にも注目して進めていかなければならない。
医師とのEメールを使用したやり取り、病院のクオリティボード、キャロルスコットさんの講義等で、アメリカの医師の考え方、 質向上のための取り組みを学んだ。おそらく日本の医師の考え方とはまったく違いオープンな考え方だと感じた。
この研修を通じ、今まで触れたことがなかったシステムや環境で考え方や視野がとても広がった。