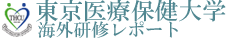

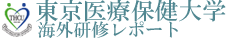

アメリカでは、ICD-9-CMが使われている。
主に、入院患者と病院の外来の診断と処置、診療所の診断と処置、医者事務所診断に使用する。
日本は、プライバシー保護法という法律が出来た。アメリカには、HIPAAという医療だけのプライバシー保護法がある。 HIPAAという法律によって、全て同じコーディングを使わなければいけないということが決められた。 法律を決めた時はまだICD-10 がなくICD-9だった。ICD-10が広く使われる前に決定したことなので、ICD-9を使用する必要があった。
ICD-9とは別にCPT-4を使っている。これは、医師の行った処置、術式の用語が書かれた物も第4版である。
アメリカでは病院に行った場合、請求書が2つ来る。1つは病院から、1つは治療した医師からの請求書である。 その請求をするために、病院はUB 04を使用し、医師はCMS 1500を使用している。
外来の場合、以下で計算される。
入院患者の場合、同様に病院と医師というかたちで2つの請求書が行くのだが、病院で1泊入院した場合、病院はCPT-4の処置でなく、 ICD-9の処置を見て記入をする。
など
このようなことが出来るようになる為には、このような疾患がどういったプロセスでどういった状態になるのかなどを理解しなければならない。
症状からどういった検査がされるのか理解している必要あり、慢性疾患(良くなることはあっても治癒することはない)についても良く知っている必要がある。
コーディングの時は、疾患の状態の部分部分をコーディングすることは出来ず、一連の疾患の状態を理解し、それに対してコーディングをしなければならない。 処置にコーディングをする際に考えることは、手術の危険性(感染など)で患者が亡くなることもあるということである。そして、それに伴うリスクに関しても知っている必要がある。 麻酔のリスクに関しては、全体麻酔か局部麻酔かなどに注意をする。 そして、処置のコーディングをするには、その処置を行うための人が特別な訓練を受けた人かどうかについても確認をする必要がある。 処置に関して密接に請求するためには、以上のようなコーディングをする必要がある。
「Punctured(刺す)」という言葉は、ICD-9には載っていないので、言い換える必要がある。この場合、「Wound(傷)」になる。 怪我をした患者には、「どのようにして、何が起こったのか」という意味のEを必ずコードする。 傷口の消毒に関するコードはない。なぜかというと、アメリカの場合、家で出来ることは請求できない。 例えば、消毒は自宅で出来るが、注射は出来ないというように。
上記よりわかるように、処置の部分が大きく違う。病院のほうでは、破傷風の注射が書かれているのに、医師のほうには入っていない。 アメリカでは、注射は看護師が行うことであり医師は行わない。そのため、医師は請求せず、病院が請求を行い、医師はERに来たという請求だけになる。
沢山の情報の中から、必要な情報を取り出すということやデータの質を考えることの大切さや難しさを知ることが出来た。 そして、それぞれの職種の役割が明確に理解され、仕事をしているということを強く感じた。医師の役割は診断して治療することである。 どのようにしたら病院にお金が入ってくるかということを、医師はよく理解していないらしい。その部分を、管理士は理解し仕事をしている。