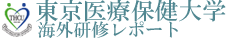

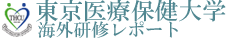

タコマコミュニティカレッジは、州立の短期大学で2年間・6学期で構成されている。修了者は准学士号が取得できる。
アメリカ人が考える「アメリカの医療制度の良い点」は以下の3点が挙げられる。
医療は「権利」か、それとも「許された特権」か、ということに関して残念ながら「権利」ではなく「許された特権」と言える。
日本は国民皆保険制度により、医療を受けることは国民の「権利」であるとされている。しかし、アメリカではお金を支払い、
医療を買う形であって「権利」になっていない。そのため、医療の質というものが非常に重要なものとされている。アメリカの医療制度は他国と大きく異なり、
複雑で全てを把握するのは困難である。
Quality = Cost VS Effectiveness + Outcomes
昔は基準や標準がなかったため、医師の判断で治療が自由に行うことができた。その結果、全体の医療費が高騰し標準化することが大切になった。
質というものは、現在証明された根拠に基づいたものをいう。情報量が増えるとエビデンスも変わってくる。
つまり医療というものは常に変化するものだと考えられる。
今までは出来高払いなどがあったが、アメリカの新しい医療の在り方としてPay for Quality=質に対してお金が支払われる医療になりつつある。 そこで、質というものはどのようにしたら計ることができるのかと考えると、医師はEBMに沿った医療を行わなければならない。 EBMとは、根拠に基づく医療のことである。医師の判断や経験だけに頼るのではなく、最新の医療技術と研究結果を加え患者の症状や 価値観に合わせて行う医療のことを言う。
アメリカでは、医療情報分析のためにICD-9以外にもあらゆるコードを使用している。病院ではICD-9、医師はCPT、研究所ではSNOMED、精神病院ではDSMⅣを使用している。 この4つのコードは1つのソフトで行われており、エンコーダーとグルーパーというコーディングを支援するソフトを使用している。
コーディングは人間が行う。最初にデータを見て数字を記入し、エンコーダーはコーディングが規則にのっとって行われているのかを コーダーに対してフィードバックする。この時重要なことはコンプライアンスをきちんと行っているかというのを見ていくことである。 その後、グルーパーによってDRG(入院患者が主疾患群によっていくらお金が支払われるのか)、APC(外来患者)などによって診療報酬が表示され仕分けをしていく。
アメリカではコーディングは非常に重要なものとしてとらえられている。なぜならHIMとしてコーディングをするときに医療記録に基づいて行うからである。 その結果、質のあるケアを行っているのかを証明している。もしコーディングがなければ誰も医療費を支払うことができない。HIMとして、 質のあるケアを提供しているという証明をコーディングによって保険者に提供する。そして保険者は、その証明に基づいて同意したならばお金を支払う、という仕組みになっている。 つまり医療に従事する人はコーディングがとても重要なものだといえる。
HIMは主に、コーディング・医療事務・法律関係・医療の監査の4つの分野で活躍している。例えば、コーディングをする人・医療事務を行う人・診療報酬の計算・規則に従った 医療が行われているのかのデータを作る人・法律について・弁護士に付いて一緒に働くなどがある。タコマコミュニティーカレッジを卒業しHIMの活躍の場所として、50%が病院、 10%が教育、3%が研究、25%が長期療養型施設、7%が医師の事務所となっている。
理論を学んだあとにスキルを学ぶ場として設けてある。
現在看護学部生は224人おり、2年間(6学期制)で養成している。それぞれのレベルに合わせた学習をしていき、今までは1学期当たり5・6回のシミュレーション練習だったが、 現在は約30回のシミュレーションを行っている。
シムマンは、1体6万5000ドル(約650万円)である。
肺音の聴診・脈の触診・瞬き・薬の投与などの機能がついている。上級編では除細動もでき、また不安に感じていることなどをシムマン自身が言葉で表現することもできる。 看護学部の教育ツールのために作られ、医療従事者の処置に対し即時にフィードバックする。すべてシナリオを作っておき、遠隔操作で行っている。シナリオというのは現段階で約130あり、 操作する技術者が日々新しいシナリオを書き増やしている。シナリオを書くためにはコンピュータを勉強し、看護学部の先生と緊密な連絡を取り合うことが重要である。なぜなら、 どのようなツールが必要かを教えてもらうことで新しいものを追加することができるからである。また解剖学的に、正確なサイズ・色・質感・現実に近いものを作りだしている。
シムマンの周辺機器にはカラー液晶ディスプレー画面があり、生理学的パラメータを正確にフィードバックする。
シムマンで学ぶことで、チームワークやコミュニケーション能力が向上し、また医療の質を高め、現場に出てから効果があると言われている。病院側から感謝されていることも1つの成果と言えるだろう。


HPSマネキンは7体ある。(新生児、妊婦、子ども、成人の女性、成人の男性)
OSは3種類あり、Mac・Apple・Linuxを使用しているが、コンピュータ同士をつなげることは非常に困難である。


シムマンで学んでいるときの授業は、ビデオに撮りWEBで公開されている。そのため、授業後にもう一度見て復習することができる。
今後の目標として、将来大規模な「病院の模型」をつくりコーディングもできるように電子カルテも作成したいと考えている。 大規模にするときに、このシミュレーションに救急車の隊員も加わり救急医療処置のトレーニングを行う計画である。例えばレントゲンが必要となったら、 看護師のもとにX線技師を呼び、またラボで行うことも出てくるだろうといわれている。あらゆる医療従事者を対象とした幅広いトレーニングを考えている。
課題点として、シナリオのプログラムを書ける専門家が少ないことである。ワシントン州では、現段階で5人しかいない。よってシミュレーションを買ったは良いが、 使いこなしていない場合が多い。他の大学では、看護学部の先生達が考えているためプログラムを書ける専門家がいると助かると言われている。
雇用市場は小さいが、将来性は高いと言える。
現在タコマコミュニティカレッジでシナリオを製作している専門家は自分が書いたプログラムを公開し、他の専門家を招いて話し合いや見学を行い普及に努めている。
アメリカでは、医療の質について重点的に考えられているということがわかった。医療費に多くのお金を投資しているにも関わらず、世界で37位であるため、 医療費の有効性については今後の課題だと感じた。
シムマンの見学は、非常に興味を持った。様々な高性能な機能がつき、看護師になる前に様々な症例に対し練習ができる点で非常に優れていると思う。 日本でも、シムマンのシナリオのプログラムを書くシミュレーション技師というスタッフの存在が重要になってくると思う。 電子カルテの互換性については、コンピュータの種類やアップデート時期が千差万別のため標準化することが大切になっていることがわかった。